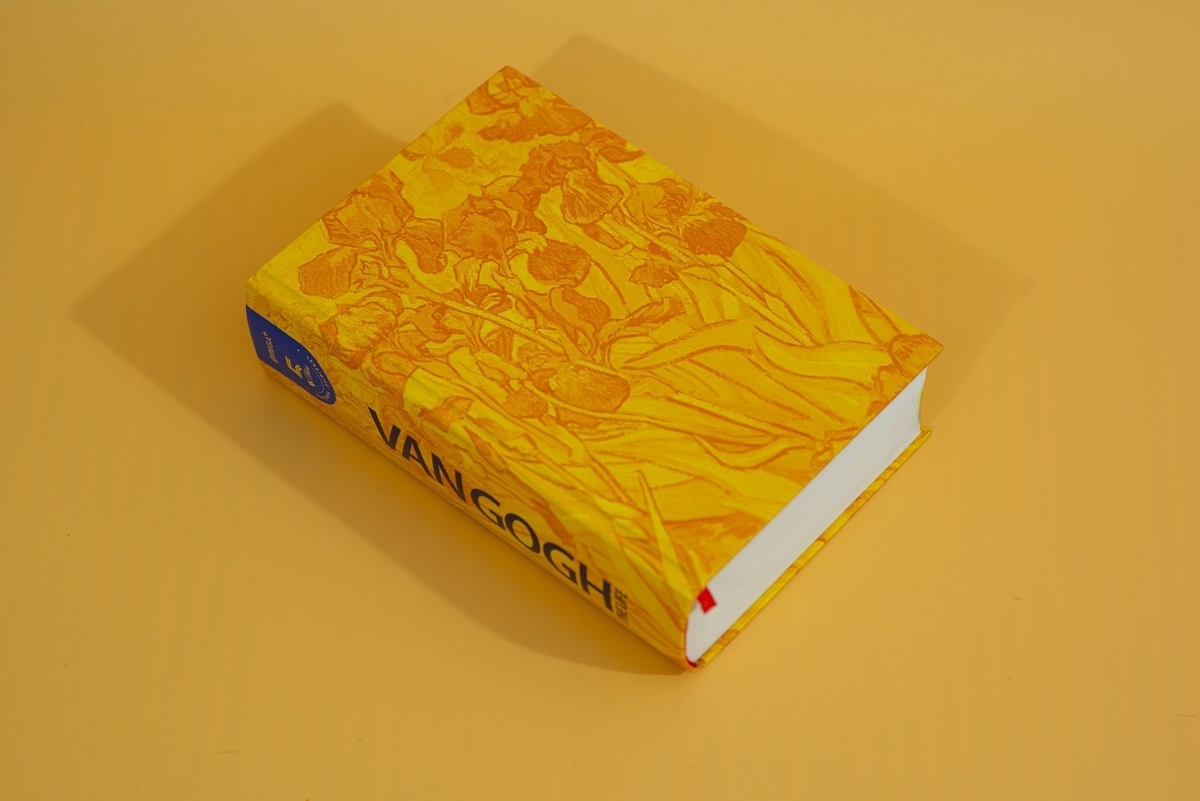僕は作家志望の人間だ。自作を書いて、小説の賞の公募に送っている。
ただ最近、実力がついたのでかえって不安になってきたことがある。それはもし受賞して本が世に出ても、売れないのではないかという不安である。捕らぬたぬきの皮算用だが、そういう不安を感じる。
まあ、まず売れないだろう。先日は小説野性時代新人賞に自作を送った。その作品にはエンターテイメント性があって、あらすじにもインパクトがあるのだが、世に出ても大して売れないだろうな、という気がする。今の人は本を読まない。僕だって読まない。ここ五年ぐらいはほとんど本屋に足を運んでいないぐらいだ。世間では本屋はどんどん潰れていっているが、それはそうだろうなと思う。本なんて、誰も読みたくないもの!
そうした社会の中でまず僕がやるべきなのは、現状の分析だろう。人の心と自分自身の心を分析する必要がある。なぜ人々は、そして僕は本を読まないのだろうか?
すると浮かび上がってくるのは、ともかく今は「ヤバい」世相だということだ。日本社会はもう長い間沈んでいっている。あと何十年間かは浮上する気配がない。より正確に言うと、弱者は死ね、という世界になっていっている。実相はもちろんのこと、世論というか、人々の合意としてそうなっている。弱い人とか、現実とかけ離れた理想を言う人とかを排除する雰囲気が醸成されていっている。それは誰もが生き残りに必死にならざるを得ない社会だ。
そうした中でがっちりとした格好をした物語を読むだけの余裕は、人々にはもはやないだろう。だから本は売れない。みんな自分のこと、目の前のことに必死なのだ。僕だってそうである。僕が金もしくは時間を支払うコンテンツは、ほとんどがVtuberのライブ配信か、短いコメディ的な話の繋がりで成り立っているような漫画に限られる。正統で重厚な物語を読む気が起こらない。それが正直なところである。コンテンツが「面白ければ売れる」というのは嘘だろう。むしろ「面白い方が売れない」。それが実際のところだろうな、と僕は思う。ユゴーの『ノートルダムドパリ』のような物語がウケるとは到底思えない。
もう少し掘り下げてみよう。今の時代は誰もが生き残りに必死である……と言ったが、これは半分嘘だ。実は、今の時代は「誰もがお互いに殺し合っている」のだ。お前が死ねば俺は助かる、とみんなが無意識レベルで思っている。かなりはっきりとそう思っている。そういう精神状態の人が多数派になると、物語というのはなかなか浸透していかないのだ。それはなぜか?
物語とは、人々が無意識レベルで諦めたことを作家がすくいあげることで開始される。前回の記事で書いたことだが、たとえばナチスに囚われたユダヤ人の子供が生きることを諦めて、死の向こう側に救いを求めるときに、蝶の絵は描かれる。希望が折れるところに諦観があらわれ、諦観が集まって別の形を得るときに、物語は登場する。
ひるがえって「誰もがお互いに殺し合っている」状態について思いを馳せると、これはなかなか諦めきれていない状態だと言える。生き残ることに諦めがついていないので、最後の手段として相手を殺そうとしているわけだ。そういう人たちに蝶の絵を差し出しても説得力は全然ない。むしろ「馬鹿を言うな」と怒られてしまうだろう。「俺は生きるぞ」と反駁される。彼らの前にはどこまでいっても現実しかない。
こうした心理状況について我々は思いをいたす必要があるだろう。だから、たとえば「人を殺さざるを得ない人」が何を諦めているのかを推測して、それを物語に描けば、ウケが取れるかもしれないという推測が成り立つ。そうしたことを僕は成していきたい。無論、その目的は僕自身が生き残っていくことだ。